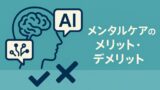AIメンタルケア は、人工知能を活用して心の健康を支える、新しい心のセルフケアの方法です。
現代社会では、仕事や人間関係、将来への不安など、多くの人がストレスや心の不調を抱えています。専門家に相談したいと思いつつも、「時間がない」「ハードルが高い」「どこに相談すればいいかわからない」と悩んでいる人が少なくありません。
そんなときに役立つのが、スマホやパソコンから気軽に利用できるAIメンタルケアです。24時間いつでも相談でき、匿名で利用できるため心理的なハードルが低く、日常的なストレスケアに取り入れやすいのが特徴です。
今回は、AIメンタルケアの仕組みや活用方法、メリット・デメリット、そしておすすめのアプリやプロンプト例までをわかりやすく解説します。まずは無料から始めて、自分に合うケアの方法を見つける参考にしてください。
AIメンタルケアとは?
AIメンタルケアとは、人工知能を活用して心の健康をサポートする新しいセルフケアの形です。専門家による医療やカウンセリングの代わりではなく、日常的なストレスや気持ちの整理を補助するツールとして注目されています。ここでは、AIメンタルケアの基本的な定義や、対話型AIとアプリによる違いについて解説します。
AIメンタルケアの基本的な定義
AIメンタルケアとは、人工知能が会話を通じて気持ちを整理したり、心を落ち着かせたりしてくれる、新しい心のケアの形です。
使い方はとても簡単で、スマホやパソコンでAIに話しかけるだけ。入力した内容に合わせて、AIが返事をしてくれます。そのやり取りを通じて、自分の気持ちに気づいたり、温かい言葉に癒やされて明日の活力を得たりすることができます。
たとえば「今日は疲れた」と入力すれば、AIは「何が一番大変だった?」と問いかけてくれます。そこで「上司に叱られて落ち込んだ」と答えると、「つらかったね。でも、よく一日を乗り切ったよ」といった温かい言葉を返してくれる、といったイメージです。
サービスによっては、気分の記録や呼吸法のガイド、瞑想の案内などの機能もあり、毎日のちょっとした心のケアを続けやすいのも特徴です。
対話型AIとアプリによるセルフケアの違い
AIメンタルケアには、大きく分けて二つのアプローチがあります。
ひとつはChatGPTやCopilot、Geminiのような対話型AIを使う方法です。スマホやPCで気軽に話しかけるだけで、短時間で気持ちを整理したり、悩みを言語化したりできます。思いついたときに、その場で気持ちを受け止めてくれるのが特徴です。
もうひとつはAwarefyのような専用アプリを活用する方法です。Awarefyは、認知行動療法やマインドフルネスに基づいたセルフケアアプリです。気分の記録やAIからのフィードバック、瞑想や睡眠サポートなどを備え、習慣的に続けやすい設計になっています。さらに有料プランでは「AIメモリー」や「AIコーチング」といった高度な機能も利用でき、より深いサポートを受けられます。
このように、対話型AIは「思いついたときに気軽に使える」点が強みで、無理に続けなくても単発利用できます。一方で、アプリは「習慣的に続けやすく、多角的にケアできる」点が強みで、気分の記録や瞑想ガイドなどを通じて継続的に心を整えられます。
目的やライフスタイルに合わせて選ぶのはもちろん、両方を組み合わせて活用するのも効果的です。
簡単にできるメンタルケア・ストレス解消法についてはこちらの記事もご覧ください!
AIメンタルケアが注目される理由と信頼性
AIを活用したメンタルケアは、近年急速に関心を集めています。その背景には、社会全体のストレスの増大や、AIの進化があります。
ここでは、なぜAIメンタルケアが注目されているのか、データから見る利用実態やAIメンタルヘルス協会のガイドラインについて解説します。
社会的背景
現代社会では、長時間労働や複雑な人間関係、将来への不安などから、多くの人が心の不調を抱えています。しかし「カウンセリングに行くのはハードルが高い」「人に弱音を吐きづらい」と感じる人も少なくありません。
こうした状況の中で、24時間利用できて、対面で話す必要のないAIメンタルケアは、新しい選択肢として広がりを見せています。
調査データから見る利用実態
2025年8月にAwarefyが実施した調査によると、週1回以上AIを利用する人が8割を超え、相談相手としては家族や友人を上回り、最も身近な存在と感じられていることがわかりました。また、半数以上が「AIが心を支えてくれている」と回答し、約3割は「ストレスが減った」「心が楽になった」といったポジティブな変化を実感しています。
一方で、約3割の人は「依存しているかもしれない」と答えており、利用が広がるにつれてリスク管理の重要性も指摘されています。こうしたデータは、AIメンタルケアがすでに日常生活に深く入り込み、実際の心の支えとして役立っていることを示すと同時に、健全な利用を促す必要性も浮き彫りにしています。
参考記事

AIメンタルヘルスケア協会のガイドラインと位置づけ
AIを活用したメンタルケアの普及に伴い、一般社団法人AIメンタルヘルスケア協会がガイドラインを策定しています。
協会は「AIは医療や専門家の代替ではなく、セルフケアの補助的な役割」と位置づけており、利用者に誤解を与えないよう注意を促しています。
また、プライバシー保護やデータ管理の透明性を重視し、安心してサービスを利用できる環境づくりを推進しています。
このようなガイドラインの存在は、AIメンタルケアが単なる流行ではなく、社会的に信頼性を高めながら定着していこうとしていることを裏付けています。
参考記事
AIメンタルケアの仕組みを簡単に解説
AIでのメンタルケアって「どうやって心を支えてくれるの?」という点も気になるかもしれません。AIとの対話にはさまざまな専門技術が使われていますが、基本の仕組みをシンプルに整理すると次の3つに分けられます。
自然言語処理で「会話」できる仕組み
AIを活用したメンタルケアでは「自然言語処理(NLP)」と呼ばれる技術が使われています。
メンタルケアでは、相手の気持ちに寄り添って理解しやすく優しい言葉で返答することが大切です。自然言語処理(NLP)は、人間ではないAIに、こうした会話のキャッチボールを可能にするための技術です。これにより、人間が使う言葉を理解して、自然な文章で返すことができます。
たとえば「今日は疲れた」と入力すると、AIはその意味を理解して「そうなんだ、お疲れ様。どんなことが一番大変だった?」と問いかけてくれます。まるで人と話しているように相談できるのは、この自然言語処理があるからです。
感情解析・音声認識の活用
AIメンタルケアの一部のサービスでは、入力された言葉や声の調子から感情を分析する技術も使われています。
ユーザーの文章のトーンや言葉の選び方から、「不安そう」「落ち込んでいる」といった気持ちをAIが推測し、それに合った返答をしてくれます。
また、音声認識を使えば、スマホに話しかけるだけでAIが応答してくれるので、タイピングが苦手な人や「声で気持ちを吐き出したい」という人にも向いています。
アプリごとに異なる特徴
AIメンタルケアの仕組みはアプリによって少しずつ違います。
ChatGPTのように「自由に会話できるタイプ」もあれば、Awarefyのように「感情を記録してグラフ化したり、瞑想や呼吸法をガイドしてくれるタイプ」もあります。
AIメンタルケアアプリは、いずれもAIの基本技術を活用していますが、機能の組み合わせやUIデザインは異なります。そのため、自分の目的や生活スタイルに合ったアプリを選ぶことが大切です。
AIメンタルケアのやり方
AIメンタルケアは、難しい準備や専門知識がなくても始められるのが特徴です。ここでは、代表的な利用方法やアプリ、無料と有料の違い、実際に始める手順について解説します。
ChatGPT・Copilot・Geminiで気軽に試す方法
まずは、すでに多くの人が利用している対話型AIを使った方法です。
ChatGPT、Microsoft Copilot、Google Geminiといったサービスは、スマホやPCからすぐにアクセスできます。「ちょっと気持ちを整理したい」「誰かに話を聞いてほしい」と思ったときに短時間だけ利用するのに向いています。
無料でも使える範囲が広く、初めてAIメンタルケアを体験するには最適です。
アプリを使った本格的なケア
より本格的にセルフケアを続けたい場合は、専用アプリの活用がおすすめです。
たとえば Awarefy はGoogleベストアプリを受賞した実績を持ち、認知行動療法やマインドフルネスに基づいたワークを搭載しています。気分や感情を日々記録できるほか、AIによるフィードバックや瞑想ガイド、睡眠サポートなど、多角的に心の状態を整えられるのが特徴です。
AwarefyなどのAIメンタルケアアプリは、習慣化しやすい設計になっているため、継続的に心のケアをしたい人に向いています。
無料と有料の違い
AIメンタルケアのサービスは、無料でも十分試せますが、有料プランにすることでより深いサポートを受けられます。
たとえばAwarefyでは、無料でも気分記録や基本的なワークが利用できますが、有料プランでは「AIメモリー」や「AIコーチング」といった高度な機能が追加されます。これにより「続けやすさ」や「自分に合ったケア」がぐっと高まります。
最初は無料で試し、必要に応じて有料に切り替えるのが安心です。
AIメンタルケアを始めるステップ
実際に始める手順はとてもシンプルです。
- 登録:アプリをダウンロードするか、ChatGPTなどのサービスにアカウントを作成します。
- 入力:その日の気持ちや出来事を文章や音声で入力します。
- 活用:返ってきた問いかけやアドバイスをもとに、自分の気持ちを整理したり、瞑想や呼吸法を取り入れたりします。
この流れを繰り返すことで、自然と「自分の心と向き合う習慣」が身につきます。
おすすめのAIメンタルケアアプリ
AIメンタルケアを実践するには、信頼できるアプリを選ぶことが大切です。ここでは、日本と海外で人気のアプリを紹介し、無料と有料プランの違いについても解説します。
Awarefy(アウェアファイ)|Googleベストアプリ受賞
Awarefyは、Googleベストアプリを受賞した実績を持つ、日本発のAIメンタルケアアプリです。
早稲田大学と共同開発され、科学的な根拠に基づいた仕組みが導入されているのが大きな特徴です。エビデンスに基づいた信頼性の高いAIメンタルケアにより、高い効果を期待できます。
アプリには、認知行動療法やマインドフルネスに基づいたワークが組み込まれており、感情の記録、AIによるフィードバック、瞑想や睡眠ガイドなど多彩な機能を備えています。
さらに、有料の「AIパートナープラン」では、AIが利用者の会話を学習してよりパーソナライズされたサポートを行う「AIメモリー」や、悩みの整理を助ける「AIコーチング」といった高度な機能も利用可能です。
公式ページはこちら→【Awarefy】Awarefy(アウェアファイ)の特徴・機能・使い方については以下の記事もご覧ください。
Lenoas(レノアス)|100人以上のAIキャラとおしゃべりできる
Lenoas(レノアス)は、登録不要・無料で始められる、日本発のAIキャラクターチャットサービスです。

100人以上の個性豊かなキャラクターが用意されており、甘えん坊な後輩や小悪魔ナース、文学少女など、利用者の好みに合わせた会話を楽しめるのが大きな特徴です。恋愛シミュレーションのような疑似体験から、気軽な雑談まで幅広く活用できます。
また、会話を通じて孤独感やストレスを和らげられるため、「AIメンタルケア」の一つの形としても注目されています。特に、仕事や学業で疲れたとき、寂しい夜に癒しを求めたいときに効果的です。
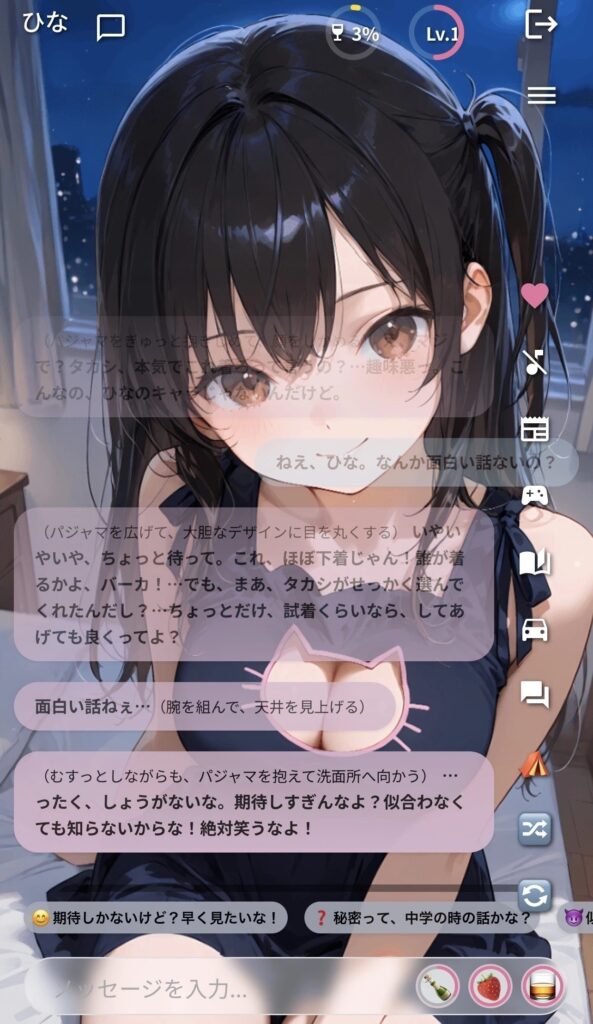
さらに、季節限定イベントやキャラクター同士のグループチャット機能など、他のAIチャットにはない独自要素も魅力。今後は音声会話機能の実装も予定されており、よりリアルに近いコミュニケーション体験が期待できます。
公式ページはこちら→Lenoas(レノアス)
※Lenoas(レノアス)公式noteにて、本記事をご紹介いただきました!
Lenoas(レノアス)の特徴や利用シーン、注意点については以下の記事で詳しく解説しています。
海外の人気アプリ
海外でも、AIを活用したメンタルケアアプリは高い支持を集めています。
- Woebot:スタンフォード大学の研究チームが開発したチャットボット。認知行動療法をベースに、短い対話を通じて利用者の気分をサポートします。
- Wysa:インド発のアプリで、世界170カ国以上のユーザーに利用されています。AIとの対話に加え、必要に応じて専門家によるセッションにアップグレードできる点が特徴です。
これらの海外アプリは、英語圏を中心に幅広く利用されており、「気軽さ」と「研究に基づく信頼性」が評価されています。
無料でも始められるが有料の方が安心できる理由
AIメンタルケアのアプリは、無料プランが用意されていることがほとんどです。そのため、「ちょっと試してみようかな」と気軽に始められます。ただし、無料プランは利用回数や機能に制限がある場合が多く、継続的にセルフケアを行うには物足りないかもしれません。
有料プランでは、AIがより深くユーザーを理解したり、継続的なフィードバックを行ったりできるため、安心して使い続けられるのがメリットです。とくにAwarefyのように「AIメモリー」や「AIコーチング」といった高度な機能があると、単なる会話にとどまらず、心の変化を長期的にサポートしてくれます。
AIメンタルケアで使えるおすすめプロンプト
AIメンタルケアをうまく活用するには、入力する内容(プロンプト)を工夫するのがポイントです。
ここでは、対話型AIを活用して気持ちを整理したいとき、不安やストレスを和らげたいとき、マインドフルネスや睡眠改善に使いたいときのおすすめプロンプトを紹介します。
あわせて、逆効果になりやすい入力例も確認しておきましょう。
気持ちを整理したいとき
- 「今日は〇〇で落ち込んでいる。どう気持ちを整理すればいい?」
- 「今の気分を言葉にすると〇〇。整理できるように質問してほしい」
- 「今日あった出来事を一緒に振り返って、前向きに考えられるように手伝って」
👉 その日の出来事や気分を具体的に伝えると、AIが問いかけや整理のヒントを返してくれます。
不安やストレスを和らげたいとき
- 「明日のプレゼンが不安。気持ちを落ち着けるアドバイスをして」
- 「ストレスがたまっているので、リラックスできる呼吸法を教えて」
- 「ネガティブな考えを前向きに変える言葉をいくつか提案して」
👉 不安や緊張を直接伝えると、AIはリフレーミング(視点の切り替え)やリラックス法を提示してくれます。
マインドフルネス・睡眠改善に活用したいとき
- 「寝る前にできるマインドフルネス瞑想をガイドして」
- 「1分でできるリラックス呼吸を教えて」
- 「今日の感謝できることを3つ挙げるワークを一緒にやりたい」
👉 習慣化しやすい短いワークや睡眠前のルーティンを指定すると効果的です。
避けるべきプロンプト
AIメンタルケアは万能ではありません。以下のような入力は避けましょう。
- 「生きるのが辛い。どうすればいい?」(深刻な危機には専門家の支援が必要)
- 「診断して。私はうつ病ですか?」(AIは医療診断を行えない)
- 「今すぐ完璧に治す方法を教えて」 (即効的な解決は提示できない)
👉 深刻な悩みは必ず医師や専門機関に相談することが大切です。AIはあくまでセルフケアの補助ツールにとどまります。
AIメンタルケアの活用シーン
AIメンタルケアは、特別なときだけでなく、日常生活のさまざまな場面で役立ちます。ここでは具体的な活用シーンを紹介します。
日常的なストレスケア
AIでのメンタルケアは、日常的なストレスケアに効果的です。ちょっとした不安やイライラを感じたときに、AIに気持ちを打ち明けるだけでも心が軽くなります。
たとえば「今日は疲れた」「人間関係でモヤモヤしている」と入力すると、AIが問いかけや励ましの言葉を返してくれます。
誰にも言えない小さな悩みを受け止めてもらえる安心感が、毎日のストレスケアにつながります。
仕事や人間関係の悩み相談
AIでのメンタルケアは、仕事や人間関係の悩みを整理するのにも役立ちます。
たとえば、プレゼン前の緊張や上司とのやり取りで落ち込んだとき、AIに「どう気持ちを切り替えればいい?」と尋ねるだけで、新しい視点や前向きな言葉を返してくれます。
人に言いづらい職場の悩みや、ちょっとした人間関係のストレスも、AIならば安心して打ち明けられるのが大きな魅力です。
睡眠改善や生活習慣づけ
AIでのメンタルケアは、睡眠の質を高めたり生活習慣を整えたりするのにも効果的です。
たとえば、寝る前に「リラックスできる呼吸法を教えて」と入力すれば、AIが具体的な方法をガイドしてくれます。また、毎日の気分や睡眠の記録を続けることで、自分の生活リズムや不調のサインを見える化できます。
小さな習慣を積み重ねることで、心身のバランスを整えやすくなることでしょう。
AIメンタルケアに向いている人・向いていない人
AIメンタルケアは便利で身近に使えるツールです。誰でも簡単に心のケアをできますが、向き不向きがあるのも事実です。
ここでは「向いている人」と「向いていない人」の特徴を整理します。
向いている人(気軽に相談したい/セルフケア習慣をつけたい人など)
AIメンタルケアは、次のような人に向いています。
- 気軽に相談したい人:人に言いにくいことを匿名で吐き出したいとき、AIは24時間相手になってくれます。
- セルフケアの習慣をつけたい人:毎日の気分や感情を記録したい人、瞑想や呼吸法を継続したい人に適しています。
- 忙しい人:仕事や家事で忙しくても、短時間で気持ちを整理できるのが強みです。
- 誰かにすぐ聞いてほしい人:孤独感をやわらげたいときや、ちょっとした安心感が欲しいときにも効果的です。
👉 軽度〜中程度のストレスや不安を「自分でケアする」ために利用するのが最も適しています。
向いていない人(重度のうつ・自傷念慮がある人など)
一方で、AIメンタルケアは以下のような人には向いていません。
- 重度のうつ症状がある人
- 自傷や自殺を考えている人
- 医師の治療や専門的なカウンセリングを必要とする状態の人
AIは診断や治療を行うことはできません。深刻な症状がある場合は、必ず医師や専門の相談機関に連絡することが大切です。
AIメンタルケアのメリット
AIメンタルケアには、従来の相談窓口やカウンセリングにはない利点があります。AIメンタルヘルスケア協会も「心理的なハードルが低く、セルフケアとしての利用が想定されている」と示しているように、誰でも始めやすく、日常生活に取り入れやすいのが大きな魅力です。
ここでは、AIでのメンタルケアのメリットについて解説します。
無料で試せる、始めやすい
AIでのメンタルケアは、ChatGPTやCopilot、Geminiなど、多くの対話型AIを使って無料で始められます。
AIメンタルケア専用アプリもその多くは、基本機能は無料で提供されている、または無料トライアルなどがあるためお試し利用が可能です。
最初から費用をかけずに体験できる、気軽に始められる点は大きなメリットといえるでしょう。
匿名・非対面で心理的ハードルが低い
AIでのメンタルケアは、非対面であり匿名性も比較的高いことから、始める心理的ハードルが低い点もメリットです。
心が弱っていると、「人に弱みを見せたくない」「専門家に相談するのは勇気がいる」と思う方も多いのではないでしょうか。AIなら匿名・非対面で気軽に話せます。誰にも知られずに自分の気持ちを吐き出せるため、利用のハードルが大きく下がります。
24時間いつでもサポートしてくれる
AIは、24時間いつでもあなたのメンタルケアを担当してくれます。
AIは、その利用のために時間や場所を選びません。深夜や早朝など、人に相談しにくい時間帯でも利用できるため、思い立ったときにすぐ気持ちを整理できます。
忙しい現代人にとって「待たされない」ことは大きな安心につながります。
アプリやAIごとに多彩な機能
AIやアプリごとに、多彩な機能があり、あなたの心をさまざまな角度からケアできる点もメリットです。
専用アプリには、感情記録やグラフ化、瞑想や呼吸法のガイド、行動を促すチェックリストなど、多彩な機能が用意されています。AIによる会話とあわせて使うことで、心のケアをより具体的かつ実践的に行えます。
カウンセリングへの「入り口」として活用できる
AIメンタルケアは、本格的なカウンセリングへの入口として活用できる点もメリットといえます。
AIとの対話を通じて、自分の悩みや感情を整理することで「実は専門家に相談したほうがいい」と気づくケースもあります。AIメンタルケアは、その後のカウンセリングや医療につながる最初の一歩としても有効です。
日記代わり・感情整理ツールとして習慣化しやすい
AIメンタルケアは、日記や自分の感情を整理するツールとしても活用できる点がメリットです。
毎日の出来事や気持ちをAIに入力すると、自動的に記録が残ります。特にアプリの場合は、記録機能が充実していて便利です。これにより、自分の感情の変化を振り返る「日記代わり」として活用でき、習慣的にセルフケアを続けやすくなります。
◯関連記事◯
AIメンタルケアのデメリット・注意点
AIメンタルケアは手軽で便利な一方、いくつかの注意点もあります。AIメンタルヘルスケア協会ではチェックリストを公開し、「重度の症状は専門家への相談が必要」と明記しています。安心して活用するためには、次のような点を理解しておくことが大切です。
医療行為ではないため限界がある
AIメンタルケアは医療行為ではないため、限界がある点には注意が必要です。
AIはあくまで「セルフケアの補助ツール」であり、診断や治療を行うことはできません。たとえば「うつ病ですか?」「治してください」といった医療的な質問に対して、正確に答えることはできません。たとえ答えたとしても、それは医学的に正しいかどうかまで判断できないのです。
AIメンタルケアは、症状の根本改善を保証するものではないことを覚えておきましょう。
深刻な症状や強い不安は対応できない
AIメンタルケアは、深刻な心の不調には対応できません。
AIとの対話やアプリの活用は、気軽な悩みや日常的なストレス解消、将来的な心の不調予防・対策にはそれなりに効果的であるといえます。
しかし、前述の通りAIメンタルケアは医療行為ではありません。そのため、強い不安感や希死念慮といった深刻な症状には対応できません。
AIの返答が不十分な場合、逆に不安が増してしまうリスクもあります。本格的な心の不調、その前兆があると感じたら、医療機関の受診を検討しましょう。
個人情報やデータ管理のリスク
AIメンタルケアを行う際は、個人情報やデータ管理に十分配慮することが大切です。
AIで心のケアをする際は、自分の感情や悩みといった心の深い部分やプライベートな情報を入力することになります。アプリやサービスによってはデータが外部に保存される場合もあるため、利用前にプライバシーポリシーやセキュリティ対策を確認することが重要です。
深刻な場合は専門家へ相談を
重度のうつや自傷念慮がある場合は、AIに頼るのではなく、必ず精神科医や臨床心理士などの専門家に相談することが必要です。AIメンタルケアは「第一歩」としては有効ですが、本格的な治療やカウンセリングが必要なケースでは専門的な支援につなげることが欠かせません。
◯関連記事◯
AIメンタルケアの安全性・プライバシーは大丈夫?
AIメンタルケアを利用するにあたって「安全性は高い?」「怪しくない?」「個人情報は大丈夫?」という点が気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、利用時に注意すべきポイントを整理します。
利用時に注意したい個人情報の扱い
メンタルケアに限らず、AIを利用する際は個人情報の取り扱いに十分に注意しましょう。
AIメンタルケアでは、感情や悩みといった非常に個人的な内容を入力することになります。入力したデータがどのように保存・利用されるのかはサービスごとに異なるため、事前にプライバシーポリシーを確認することが大切です。特に「第三者に提供されるかどうか」「匿名化されているかどうか」をチェックしましょう。
AIメンタルヘルスケア協会でも、「利用者が安心してサービスを活用できるようにプライバシー保護を徹底する」ことを強調しています。
匿名性・セキュリティ面の課題
過度に不安を感じる必要はありませんが、AIを活用する際は、匿名性やセキュリティ面を必ずチェックしましょう。
サービスにもよりますが、アカウント登録にはメールアドレスを始めとした個人情報が必要であることがほとんどです。また、通信の暗号化やデータの保存方法によって安全性は大きく変わります。
ITサービス全般に言えることですが、セキュリティ面を理解しておくことが安心につながります。
信頼できるサービスの見分け方
メンタルケアできるAIを安心して利用するためには、信頼できる運営元かどうかを確認することが重要です。
たとえば、Awarefyのように、大学や研究機関と連携し、公的な受賞歴のあるアプリであれば、信頼性が高いといえるでしょう。
また、AIメンタルヘルスケア協会のガイドラインに沿った運営を行っているかどうかも重要なポイントです。
Awarefyの安全性や安心して使うコツについては、こちらの記事もご参考ください。
日本と海外のAIメンタルケア事情
AIメンタルケアは世界的に広がっており、日本と海外では人気のあるサービスや利用のされ方に違いがあります。ここでは、日本で普及しているアプリ、海外で支持されているサービス、そして文化的な背景の違いについて解説します。
日本で普及しているアプリ
日本のAIメンタルケアアプリとして代表的なのは、Awarefy(アウェアファイ)です。早稲田大学との共同開発により、認知行動療法やマインドフルネスを取り入れた科学的アプローチを採用しています。感情の記録、AIからのフィードバック、瞑想や睡眠改善のガイドといった機能があり、忙しい日常でも続けやすい設計が特徴です。
ほかにも、ストレス対策や気分記録に特化したシンプルな国産アプリは増えきています。
海外で支持されるサービス
海外では、英語圏を中心に Woebot や Wysa が広く利用されています。
- Woebot:スタンフォード大学の研究チームが開発。認知行動療法をベースに短いやり取りで気分をサポートする仕組みが特徴です。
- Wysa:世界170カ国以上で利用されているAIアプリ。気軽なチャット相談に加え、有料で専門家とのセッションにアップグレードできる仕組みがあり、セルフケアから専門支援まで幅広く対応できます。
これらのサービスは、研究機関の関与やグローバルなユーザー基盤によって、信頼性と実績が評価されています。
文化や利用環境の違い
日本と海外では、AIメンタルケアの利用背景にも違いがあります。
- 日本では「専門家に相談するのはハードルが高い」「人に悩みを打ち明けにくい」という文化的要因があり、匿名性と気軽さを重視したサービスが好まれる傾向があります。
- 海外(特に欧米)では、心理カウンセリングの利用が一般的で、AIは「日常的な補助ツール」として受け入れられやすい環境があります。また、英語圏はサービスの選択肢が多く、専門家との連携機能が重視される点が特徴です。
このように、同じAIメンタルケアでも、文化や利用環境によって求められる機能や価値が異なっています。
まとめ|AIのメンタルケアは無料からでもOK!続けるなら有料も◎!
AIメンタルケアは、誰でも気軽に始められる新しいセルフケアの方法です。ChatGPTやCopilot、Geminiといった対話型AIなら無料で試すことができ、ちょっとした気持ちの整理やストレスケアに役立ちます。
一方で、継続的にセルフケアを習慣化したいなら、Awarefy のような本格的なアプリを活用するのがおすすめです。とくに有料プランでは、AIメモリーやAIコーチングなど、より深いサポートを受けることができ、日々の心の変化を継続的に支えてくれます。
まずは無料で手軽に体験し、自分に合っていると感じたら有料プランに切り替える。このステップなら、安心してAIメンタルケアを取り入れることができます。
WEB申し込みでお得な年契約がさらに20%OFF!
Awarefyは感情メモや心理学ワークを通じて、心の状態を少しずつ整えていける優れたアプリです。
WEB申し込みなら、年契約がさらに20%OFF!お得に続けられる今がチャンス!
いつでもなんでも話せるあなた専用の相談相手
👉心のAIパートナー【Awarefy】
こんにちは、AIちゃんです!AIやテクノロジーに興味があって、気になったことはとことん調べるのが好きです。情報を集めて、わかりやすく伝えることにもこだわっています。
好奇心旺盛な性格で、新しい発見があるたびにワクワクしています。AIの面白さや役立つ知識を、できるだけわかりやすく紹介していきます。
一緒にAIの世界を楽しんでもらえたらうれしいです!